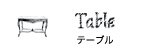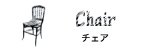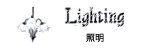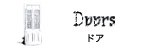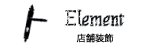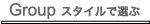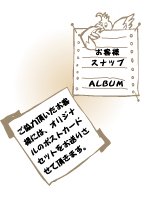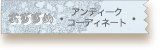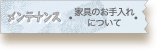- Home >
- BlogTop >
- アンティークのある暮らし
- >
- 部屋の動線はどうやって取ればいいの?
部屋の動線はどうやって取ればいいの?

どれほど素敵なインテリアであっても、使い勝手の悪い空間ではくつろぐことは出来ませんよね。使い勝手の悪い空間とは、大まかに言って以下の2つになります。
「動作をする時に動きにくい」=スペースが確保されていない空間
「動作をする時に移動する距離が長い」=スペースに無駄がある空間
部屋自体の大小は、使い勝手の良し悪しを決定するものではありません。ヒューマンスケール(人が動作をする時に必要とする空間のサイズ)と動線(人が自然に行動する時に動くだろうルート)を意識してレイアウトすれば、狭くても動きやすく、広くても無駄に動き回らない部屋づくりが可能です。
ヒューマンスケールに必要なスペース
一般的にインテリア業界では、下記の空間が確保されないと人間が動きにくいと言われています。
人が1人立つ(歩く)のに必要な幅:600㎜
人が2人立つ(歩く)のに必要な幅:900~1200㎜
人が横向きに通るのに必要な幅:300~400㎜
座った人が椅子から立ちあがるのに必要なサイズ:600㎜
キッチンで作業するのに必要なサイズ:800㎜
引出しを開けて物を出し入れするのに必要なサイズ:700㎜
キャビネットから物を出し入れするのに必要なサイズ:扉の幅+30㎜
(※いずれも家具の奥行きは含めない)
家具の配置を決める時は、これらのヒューマンスケールを考慮しなければなりません。例えば、ダイニングセットを置く場合、壁から600㎜以上離して置かないと椅子を引いて座ることができませんし、キャビネットを置く場所の前に700㎜以上の空間が無いと物を出し入れしにくくなります。
動線、自分の1日の行動を線にして考える
動線とは、部屋の中を移動する時に通る経路を指します。使い勝手のいい空間を作る時には、動線を考慮しなければなりません。
家具のレイアウトの基本は、よく通る動線は広めに取ること、無駄に動かずに行動できるように配置することです。
動線は、暮らす人によって異なりますので、まずは自分の1日の行動を線にしてみましょう。起きて、洗面(シャワー)、着替え、食事……と、自分の行動パターンを考えながら間取りの中を移動します。この時、何度も行き来する所や、物を抱えて移動する場所がメインの動線です。モノを持って移動する場合は、幅800㎜程度の空間を確保すれば、ストレスなく動くことができると言われています。
動線がシンプルなことが、使いやすい空間の目安
自分の1日の行動を線にしてみて、動線がジグザグに曲がっていたり、同じ場所を何度も行き来している場合は、無駄の多いレイアウトである可能性があります。動線が直線に近いほど、効率的に動けていると言えます。
家の中で自分が大事にしたい時間(行動)をイメージします。例えばそれが、「ダイニングテーブルでお茶を飲む」なら、「カップボードから茶器を取る」→「お湯を沸かす」→「トレーに乗せてテーブルへ運ぶ」→「テーブルに座る」という一連の動作がなめらかにできるように家具を配置しましょう。
動線を活かす工夫をすることで、家で過ごす時間が快適なものになります。また、しっかりと動線を確保することで、室内をスッキリと広く見せる効果が期待できます。
日本の住宅に合わせて作られていないアンティーク家具などは、サイズが大きかったり、暗めの色合いで圧迫感が出てしまう場合があります。購入前には室内のサイズを測るだけでなく、他の家具との兼ね合いを考慮し、動線が確保できるサイズを選ぶようにしましょう。
関連記事
アンティークのある暮らしの最新記事
-
CATEGORY : アンティークのある暮らしUPDATE : 2021/09/30
-
CATEGORY : アンティークのある暮らしUPDATE : 2019/11/30
-
CATEGORY : アンティークのある暮らしUPDATE : 2019/08/02
-
CATEGORY : アンティークのある暮らしUPDATE : 2019/08/01
 カート
カート








 失敗しないアンティーク家具の選び方
失敗しないアンティーク家具の選び方